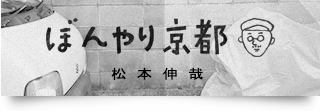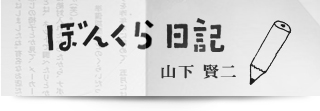【連載もの】ぼんやり京都(6)
最初のお店(レコード屋)は、10年間続けた。
廃業したのは2007年。あまり公にしていなかったとはいえ、営業最終週あたりは、本当にたくさんのお客さんが来てくれた。
もう9年も前のことですが、その節はありがとうございました。
左京区一乗寺のすみっこにある、小さいレコード屋だったが、通ってくれたお客さんには、それなりに音楽的な影響を与えたのかも知れない。大学生の頃にずっと通ってくれていたある常連さんは、最終日に東京から駆けつけてくれ、「この店は僕の青春でした」と、突然レジの前で泣き崩れ、なぜかそこに居合わせた閉店セール目当てのお客さんまでもらい泣きをしていた。
そんなちょっといい話をしておきながら、誤解を承知の上で告白すると、当事者である僕自身は、びっくりするくらい何の感慨もなかった。悲しみは1ミリもなく、むしろ、この店の呪縛から解き放たれると思うと、すがすがしい気持ちでいっぱい。ウキウキしながら閉店の日を待ちこがれていた。
以前、ある喫茶店の最終営業日に偶然居合わせたことがある。正確には、前日が最終日で、片付けをしながら、常連さんとダラダラしているところにたまたま紛れ込んでしまった。
カウンターに座ると、つるつる坊主頭の陽気なマスターが「ゴメン、今日はコーヒーしかない」と言いながら、ポットから一杯注いでくれた。
昨日が営業最終日だったことを聞いたのはこのときだった。すぐに出ようと思ったのだが、おしゃべり好きのマスターらしく、「どこから来たの?」「仕事は?」なとど、矢継ぎ早に質問をされ、お菓子などをもらったりしているうちに、すっかり店を出るきっかけを失ってしまった。
マスターはこの店のことも話してくれた。30年近くやっていたこと。今日手伝いに来てくれたのは同級生であること。バツイチであること。など、じわじわと湿っぽい方向へ話が進む。煙草のヤニとほこりでくすんだ喫茶店は、思い出に浸るには最適の環境だ。感傷的な場面は苦手なので、早くこの場から脱出したいと思ったが、マスターの話はまだまだ続く、そのうち、うっすらと涙でも浮かべられたらどうしよう。と、どきどきしていた。
しかし、いつまでたってもマスターからそんな気配は伝わって来ない。
思っているのと様子が違う。と、気付いたのは、同級生との会話からだった。どうやら、マスターは店を経営していたことで、趣味である釣りにほとんど行けないことが、苦痛で仕方なかったようなのである。
「釣りが好きなんですね」。
声をかけたら、明日早速、釣りに出かけるというではないか。集まった同級生は、なんのことはない、なかよし釣り仲間でもあった。
ひょっとしたら昨日は、いかにも最後の日らしい、大感動シーンが繰り広げられていたのかもしれない。しかし、少なくともそのときは、何か憑き物が取れたような、せいせいした空気感しか伝わって来なかった。
もうひとり、釣り仲間が入ってきたのをきっかけに、その店を後にした。
店を続ける。ということは「習慣」だ。
そこには何の感情も無い。店を開けて、閉める。そのことに疑問を持たず、淡々と続けることが、店に立つものの宿命だ。
お店をはじめてしまうと、オーナー業でもない限り、「思っていた以上に身動きが取れない」と、誰もが思うだろう。基本「待つ」ことが仕事なので、楽しいことを探しに外へ出ることも出来ない。
忙しくてもヒマでも、得体の知れない閉塞感が常にある。
好きではじめたことなので、誰にも文句は言えない。
それが、ずっと続く。
あのマスターの気持ちが、自分の店を閉めるとき、わかった気がした。
実はエピソードの細部はあまり憶えていないので、正確性には欠けるのだが、「今日はコーヒーしかないけれど」の「今日は」という言葉だけは、はっきりと憶えている。そのときは「もう明日はないだろうに」と不思議に思ったのだが、店ではない別の「明日」があったのだ。
店をやめて、そのことにはじめて気がついた。
(*注)写真の店は内容とは関係ありません。ある街で絶賛営業中です
Profile

松本伸哉