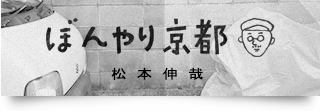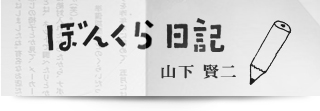【連載もの】絵そらごと〜こどもじみた大人たちへ ③ 「本屋さん」
「本屋さん」
本屋さんごっこをするときは、洗練された大人の女性客のために婦人誌、昆虫の図鑑や、かき氷機の使い方などを置いていた。裏が白い新聞の折り込み広告の紙を束ねて二つに折って、ホッチキスで留めた小さな本を毎回つくった。本屋さんごっこの演出のためだけなので表紙だけ、中身はないの。色鉛筆で表紙の絵を描いて、気の利いたタイトルをつけた。さりげなくどうでもいいところに必死に凝るのは子供の頃からの癖。メロンの絵ばーんという表紙で『おみまい』という実用書、かき氷機の本はうちにあったシロクマのかき氷機を描いて、タイトルは『シロップ』と変化球。『さなぎ』という本は神秘的な蛹の変態プロセスを図鑑から一生懸命に模写した。「変態」という言葉に少しクスッとしちゃうようになった頃である。『パンダちゃん』とこいぬのトコの、動物間の友情の摩擦を描いたサスペンスドラマもすでに書いていたので、その文庫本も店に置いた。そう、『パンダちゃん』は人気小説のため文庫化されてるの。誰も知らないところで一人、二重にも三重にもこだわっていたのである。
あの頃わたしは夢見る少女ルルとかララとかフランシーヌとかエスメラルダとかに夢中で、自分の名前も当然、本当はアンリ・ルイーゼとかシャルロッテとかなんかなはずだと確信していた。時代は70年代前~中期、いえす、ファンタジー黄金期。四畳半フォークとプログレッシヴ・ロックの湯気が絡み合う東京の西側、三鷹。杉並区保護樹林に指定されていた学校の森で、仲好しの精霊たちを追いかけ、19世紀末のヨーロッパの奇妙な寓話や岩波少年文庫を読みふけっていた。立川にある、古い洋館の友だちの家の屋根裏部屋は魔法ごっこをするのに最適で、おませなその子が好きだった男の子のことをコックリさんに聞いたりしていた。そしてそのうちわたしは、精霊たちを追いかけるのも、本屋さんごっこも止めた。その代わり、ほんとうの本屋さんに通うようになった。
その本屋さんは三鷹ネオ書房。
三鷹南口駅前通りをうちから駅の方に歩いてすぐ、漫画本が中心の貸し本屋さんだった。オスカルにも、チビ猫にも、ジルベールとセルジュにも、モンシェリcoco にも、樫の木陰でお昼寝したい小女が虜になった乙女の世界はすべてはネオ書房で出会った。ネオ書房に入ると、ふろくのおまけのビニールのような甘い香りがした。足下から天井までびっしりとポップな色の本が木の棚に分類されて並んでて、売り物の雑誌・コミック類の棚を中心に左右に女子向け貸本、男子向け貸本、と別れていた。店と奥のお茶の間を、舞台と楽屋のように暖簾が仕切り、おじさん、おばさん、大学生の息子さんが入れ替わり立ち替わり座布団の上に座っていた。舞台の上にレジはなく、小銭の入った引き出しと、大きなソロバンと、分厚いノートがあったように思う。レース編みのヘアーネットを被ったおばさんは、いつもなにか食べていた。というか、モグモグと噛んでいた。ぜったい白すぎる白粉が塗られた顔に笑顔がのそっと乗っかっていた。おじさんは、メガネの淵もポマードで固めていた髪も黒々として、大きすぎるズボンを履いていた。長年愛用しているらしい皮のベルトも黒かったと思う。びっこの足を引きずるようにして、高い所にある本も取ってくれた。おじさんは戦争で足を負傷された、と後になって知った。
中学2年生から3年生になる春休み、14歳の誕生日を迎えて3日目のあの日、わたしは『あしたのジョー』に夢中になっていた。一瞬でもジョーが切れてしまわぬように、一泊料金で借りれるだけ何巻もまとめて借りていた。借りた分をちゃんと読み終えられるように、延長料金を払わなくても良いように、夜更かしして読んでいた。読みながら眠りにつき、次の朝は10時ころに起きて、部屋のカーテンも開けずに起き抜けのベッドの中でまたジョーに浸っていた。そしてジョーと共に1日を始めた。お昼頃、借りていた分を読み終えてしまい、ジョーが切れた。すぐに自転車でネオ書房へ急ぎ、また続きをまとめて借りて家に戻ってきた。家に戻って来ると、母が叫んでいた。ちーちゃんが動揺していた。屋上のテラス、わたしの部屋の外、朝、起きて開けなかったカーテンの向こう側で、前の日から行方がわからなくなっていた父が倒れているのを、屋上に洗濯物を干しに行ったちーちゃんが見つけたのだと言う。すでに父は息をしていなかった。前の晩にこっそり帰ってきて、朝陽を見ながらお酒を飲んでいて、そのまま眠ってしまったのか。父はうずくまるように倒れていて、心臓は止まっていた。そこからは、知らない人たちがたくさんやってきて、いろんな人たちが険しい顔で父を囲んでなにかを調べたりしていた。すべてが「非日常」という残酷なお化けに変わった。わたしはもうジョーのことは忘れていた。覚えているのは、それ以上『あしたのジョー』の続きは読まなかったこと。そして朝10時、起きた時に時間を戻したかったこと。白衣を着た白髪の男の人が、父の心臓が停止したのは推定で朝の11時、と言っていたから。もしもあの時、わたしがカーテンを開けていたら、あんなにジョーに夢中になっていなかったら、部屋の外で倒れていた父を見つけられたはずだったのに。わたしはカーテンを開けなかった自分を憎んだ。ついでにジョーも嫌になった。
わたしはもうなぜかネオ書房にも行きたくなかった。ネオ書房に行く、という日常が恨めしかったのだ。ネオ書房に行く、という日常的な行為をいくらしても、あの朝、起きてカーテンを開けなかった前の日常には戻れないのだ。どうあがいてもどうせ戻れない日常ならば、その戻れない日常にはもう触れたくもなかった。14歳のあの日から、わたしはネオ書房に行かなくなり、もう漫画も読まなくなった。
実はいつからか、本屋が怖いとさえ思っている自分に気がついた。それはそこに、とても抱えきれないほどの物語や情報が詰まっていて、その内容に押しつぶされそうな気がして怖いのだ、と気がついた。こんなことあまり人に言えない。本の数だけ、いやそれ以上に人の表現や主張や物語があってこちらに語りかけてくる意識の塊である本屋。気になる本は、背表紙のタイトル、表紙の図柄を遠くからこっそり見るだけでお腹がいっぱいになり、充分に思ってしまう。手にとって開いてみるには勇気さえ必要である。いったいこんな自意識過剰さはいつから始まったのか。京都で、わたしは本や本屋に関わる友だちに囲まれている。ほんとうは、彼らと本との深く健全な関係を羨ましく思っているのに。
このたびホホホ座1周年のお祝いで、ごっこじゃないほんとうの本屋さんの店番を1時間だけすることになったので、わたしにとっての「本屋さん」を考えてみた。それは確実に、あのネオ書房だった。そしてその「本屋さん」は、ぜったいに侵されたくない少女時代の聖域として、わたしの思い出の中に大切にしまわれていた。「ネオ書房、三鷹 」で検索してみたら、なんと数年前まであったというネオ書房が出てきた。昭和3年生まれのあのおじさんはお爺さんになって、63年間もあの場所で、あの頃のまま、貸し本屋・ネオ書房を続けておられたと知った。胸がいっぱいになって、今の自分からネオ書房に、心から「ありがとうございました」と手を合わせてお礼を言った。VIVA 本屋さん。
ふろく・わたしの岩波少年文庫・心のベスト3
「最終的にはピッピがいる」くらいに思ってここまで来れた、といっても過言ではない。とにかくピッピはアナーキストで、ありえなくぶっ飛んでて、かっこいい。でもいい奴だから、大丈夫。実は臆病で気が弱いわたしは、ピッピみたいに怖いもの知らずになりたかった。サル(みたいな犬)と、お馬はいないけど、ごたごた荘みたいな家で自由に暮らしているところと、早くにみなしごになっちゃった点ではかなり近くにこれたと思う。
『みどりのゆび』
お話は言うまでもなく、絵も素晴らしい。デビルマンも、ジャングルブックのモーグリもいいけど、みどりのゆびを持つ少年チトへの気持ちも、あれは恋だったんだな。病院のベッドで寝ているあの女の子が羨ましかった。嫉妬した。悲しみや争いを、植物を生やして愛で包み込む少年。初めての反戦小説はとてもエレガントでロマンチックだったのです。
『モモ』
聞き上手は永遠の憧れなのです。わたしも亀さんという名の亀と暮らし暮らしていましたが、いつの間にか時間泥棒に時間をとられてしまったようで悔しい。気づいているだけマシなのかな。